第4回越谷ごちゃまぜの会を初のリアル交流会として開催しました
11月12日(日)に「越谷ごちゃまぜの会」初のリアル交流会を開催しました。
これは「埼玉県立大学研究開発センタープロジェクト」の一環で実施したもので、当日は約40名の方に御参加いただきました。
ごちゃまぜの会は、子ども・子育て世帯や高齢者、障害者などの支援を必要とする人を支援するNPOや社会福祉法人、ボランティア、個人、民間企業などの支援者同士をつなぎ、
個々の“点”としての取組を“面”として機能できるよう目指す取組です。
会の冒頭、本研究プロジェクトの代表であり、越谷ごちゃまぜの会の立上げ・運営を支援してきた本学の研究科/研究開発センター所属 川越 雅弘教授から、
越谷ごちゃまぜの会の趣旨説明がありました。
川越教授からは「地域課題は複合化しており多様な主体による解決が求められている」ことや「ごちゃまぜの会では参加者同士がお互いの活動を知り連携につなげてほしい」旨の話がありました。
第1部は、越谷市内で活躍されている支援者5名の方からの活動紹介がありました。
≪活動紹介の内容≫
・越谷こどもサポートネットワーク 草場澄江氏
越谷市でこども支援に関わる団体同士のネットワーク・連携の取組について、学習会・中学生の場所づくりについて紹介いただきました。
・歩未グループ 丸山悠太氏
児童発達支援・放課後デイサービス、子どもの障害を相談する環境づくり等の取組を紹介いただきました。
・就労準備サポートつながり 茂利浩幸氏
生活困窮者への支援、孤立を無くすための取組等を事例を交えながら紹介いただきました。
・民間救急・介護タクシーすまいる 鈴木明人氏
民間救急が必要とされる現状や民間救急だからこそできる活動事例等を紹介いただきました。
・越谷市地域共生部地域共生推進課 星達也氏
行政における地域共生社会づくりの取組として越谷市の重点事業等を紹介いただきました。
第2部は、参加者の1分間自己紹介スピーチと意見交換を行いました。
≪当日の様子≫



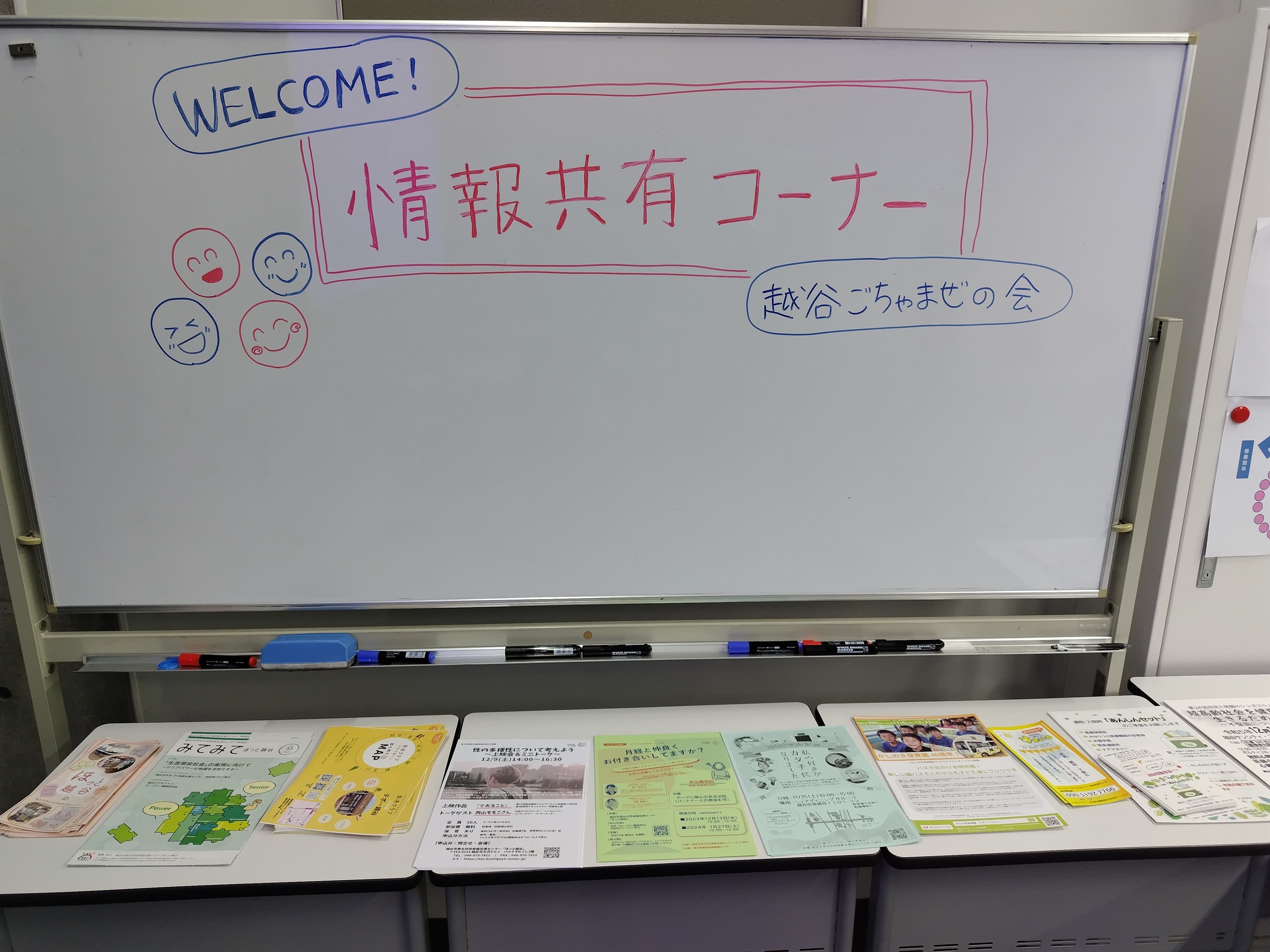
【参考】プロジェクト概要
本学研究開発センターは、地域包括ケアシステムの発展、地域共生社会の実現に寄与する地域の諸課題の解決に向けた実用的・実践的な研究として「研究開発センタープロジェクト」を複数実施しています。
その中でも「支援者(支援を要する人を支援する人)への支援」に焦点をあてたプロジェクトの一環として、2021年度からモデル市(北本市)において「ごちゃまぜの会」を定期的に開催してまいりました。
モデル市での開催の結果、参加者や地域の社会福祉協議会、生活支援コーディネーターなどのつながりが生まれ、協働しての市内ショッピングモールバスツアーやログハウスでのクラフトカフェ開催などが実現しています。