埼玉県立大学WEB講座をご覧いただきありがとうございます。
お読みいただきましたら、今後の参考に、ご意見・ご感想をお聞かせください。
お手数ですが、
こちらへご入力ください。
第28回 高齢の方や障害のある方が地域で安心安全に
暮らしていくための施設、事業、サービスについて
第28回となる今回のテーマは、「高齢の方や障害のある方が地域で安心安全に暮らしていくための施設、事業、サービスについて」です。
テーマ設定の背景
高齢の方や障害のある方が生活しづらくなった場合には、我が国においては介護保険や障害福祉などの保険制度が充実しているので、制度やサービスを利用することで生活のサポートを受ける事ができます。
これらの制度やサービスについては、ほとんどの方が内容や利用方法を知らないのが現状で、生活がしづらくなった際に、初めて知る方も多いと思います。
また、市区町村などから提供される公的なサービスだけが高齢の方や障害のある方の生活を支えているのではなく、民間事業者、地域住民の取り組みについても、内容や利用の手続きなどを知っていると、迅速かつ適切な対応ができます。
私たちは、いつでも突然に心身の状態が変化し、介護が必要になることもあり、もしもの時に、どのような施設、事業、サービスがあるのか知っておくことが大切に思います。
今回のWEB講座では、障害のあるお子さんの場合、精神に障害のある方の場合、高齢者の場合という視点で、様々な施設、事業、サービスについて解説いたします。
第27回 健康的な食生活とは
第27回となる今回のテーマは、「健康的な食生活とは」です。
テーマ設定の背景
日本は世界的に長寿の国として知られています。2023年5月19日にWHOが発表した2023年版の世界保健統計によると、日本の健康寿命は堂々の第1位です。健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことを意味します。この健康寿命を延ばすために最も大切なことの一つに日頃の食事のとり方があります。
今回のWEB講座では、健康寿命を延ばすための食生活つまり「健康的な食生活」について、「生活習慣予防」、「果物」、「機能性表示食品」の3つの視点から役立つ情報を提供したいと思います。
第26回 子育て支援の制度
第26回となる今回のテーマは、「子育て支援の制度」です。
テーマ設定の背景
本講座では、子育て支援の制度を取り上げます。まず、このテーマを取り上げることにした背景をご説明した上で、本論に入りたいと思います。
なお、本講座の執筆にあたり、評価や意見などに関する記述については、教員個人のものであり、所属する組織などとは無関係であることをあらかじめお断りさせていただきます。
未来の姿がとても見えにくくなっています。こうした不透明な状況の中でも未来を切り開く核となるのが、人的資源として総合的な力量を有する私たちひとりひとりの人間であることは言うまでもありません。
知識経済化が進む中、ますます重要になる基礎的な認知能力の獲得には、家庭をはじめとする幼少期の養育環境や教育が決定的に重要であるという指摘が多くなされています。
従来わが国では、子育ての責任は、基本的に親などの保護者が負うという考え方が支配的でした。
例えば保育所も当初は、母親が働かなくては生活できないような低所得世帯に利用者が限定されていましたし、児童手当も他の先進国に比べて創設が大幅に遅れ、給付水準も総給付費の対GDP(国内総生産)比が1%程度の主要国に比べ、2桁小さいレベル(約0.03%)に長く停滞するなど制度の存在自体が疑われるような状況でした。
仕事と子育ての両立の面でも、当初育児休業制度の対象となったのが、教師、看護師、保育士の3職種に限定されたことに表れているように、一般の女性は結婚、出産したら退職し、家庭で家事、育児を担うのが当然と考えられていました。
戦前の翼賛的な「産めよ、増やせよ」の反省から国家の出生に対する関与は、長くタブー視されてきましたが、1990年のいわゆる1.57ショック(前年の合計特殊出生率が丙午で1.58まで落ち込んだ1966年の水準を下回ったことを指す)を契機に、個人やカップルの妊娠、出産に関する自己決定権を尊重しながら、個人が希望する出産を妨げる要因を除去するものとして少子化対策が開始されました。
その後、たび重なる各種の提言などを受け、我が国の子育て支援の制度は、メニューとしては一通り出そろっているようにも見えますが、社会保障制度の給付が高齢者に偏っていることもあり、総じて実効性に乏しく、掛け声倒れ、看板倒れになっていたと言わざるを得ないように思われます。
実際、団塊の世代で約270万、団塊ジュニアの世代で約200万に達していた出生数は、コロナ禍もあって昨年80万人を下回ったとされており、少子化に歯止めがかかっていません。
急速な少子化の進行などを受け、政府は、今年度から「常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組や政策を我が国社会の真ん中に据えて、強力に進めていく」ため、内閣府の外局として子ども家庭庁を設置しました。
また、「こどもに関する様々な取組を講ずるに当たっての共通の基盤となる包括的な基本法として「こども基本法」」も施行されています。
団塊ジュニアの世代がすでに出産適齢期を過ぎていることを考えると、少子化を反転させるのは、手遅れのようにも思われますが、子育て支援の制度、政策は、少子化の進行とは関係なく総合的に拡充、推進されるべきものです。
具体的な施策の内容と実施は、従来通り、個別の各法や予算措置などに委ねられており、子育て支援の施策が、内実のある質量ともに充実したものになるかどうかは、必要な財源の確保を含め、今後の取組にかかっていると言えるでしょう。
本講座では、子どもを持つことを考えているカップルなどのために、子育て支援の制度を、読者の立場に立ってわかりやすく紹介し、判断材料を提供することを目的にしています。
具体的には、多岐にわたる子育て支援の制度から、特に重要な1.子育ての経済的支援、2.育児と就労の両立支援、3.保育関連の制度の3つを取り上げ、それぞれを専門とする本学の教員から丁寧に説明してもらおうとするものです。子どもを持つことを考えている皆さんなどのお役に立つ情報が提供できれば幸いです。
第25回 健康寿命を伸ばすには
第25回となる今回のテーマは、「健康寿命を伸ばすには」です。
テーマ設定の背景
近年、「健康寿命」という言葉を見聞きする機会が増えています。もともと世界保健機関(WHO) が提唱した概念で、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されています。簡単にいうと、介護などに頼らずに自立して生活できている健康な期間のことです。
今や日本は世界一の長寿国となり、平均寿命が延びる中、最後まで健康で生きたいと誰もが思っています。厚生労働省では3年ごとに健康寿命を発表しており、2021年に発表されたデータによると、2019年の健康寿命は男性が72.68歳、女性が75.38歳でした。一方、2019年の平均寿命は男性が81.41歳、女性が87.45歳です。比較すると、男性は約8.73年、女性は約12.07年の差があり、健康寿命のほうが短く介護を必要とする年数が約8~12年必要という結果となっています。
健康寿命を伸ばす効果的な対策には、自立出来ている健康な時から生活習慣を見直すことが重要です。今回は専門の先生に、「ストレス」「運動」「口腔」の3つの視点から教えて頂きたいと思います。皆様の健康寿命が伸びますように!
出典:WHO「Life expectancy and Healthy life expectancy Data by country」
※2019年男女平均の数値 https://apps.who.int/gho/data/view.main.SDG2016LEXv?lang=en
第24回 ストレス社会を生きる知恵
第24回となる今回のテーマは,「ストレス社会を生きる知恵」です。
テーマ設定の背景
長引くコロナ禍の影響だけでなく、少子高齢社会の到来や貧困、格差、戦争等による社会不安の増大といった様々な問題が山積している2022年の日本はストレス社会と言えるでしょう。ストレス社会を生きる我々にとって日々のストレスとの付合い方は生きる上で重要な視点と言えます。今回は「セルフメディケーション」、「運動」、「うつ病」の3つの視点から,ストレス社会を生きるための知恵を提供
したいと思います
第23回 肩・腰・膝の痛み
第23回となる今回のテーマは,「肩・腰・膝の痛み」です。
テーマ設定の背景
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の収束を願いつつ、家で過ごす時間が長くなった方も多いのではないでしょうか。
どのような状況であっても、何事もなく健やかな日々を過ごされるのが一番です。
しかし、不活発などの要因で運動器に不具合を生じた方も実際いらっしゃるのではないでしょうか。特に、肩・腰・膝の痛みは、種々の活動の制限を来たすことでも広く知られています。
そこで、本学の理学療法士 3 名が、専門的立場から運動器、とりわけ「肩」「腰」「膝」の痛みとその対処法について具体的なアドバイスを提示します。
今は何ともない方から、症状の軽い方・重い方まで、一読の価値ありです。
それでは、どうぞお楽しみください。
第22回 自分らしい生活を可能にする福祉機器
第22回となる今回のテーマは,「自分らしい生活を可能にする福祉機器」です。
テーマ設定の背景
超高齢化社会を迎え,介護は身近な存在となっています。障害の有無に関わらず,福祉機器の活用によって,自分らしい生活を継続,維持する可能性が拡がり,また介護者も介護負担を軽減し自分らしい生活ができる一助となることと思います。
そこで今回のWeb講座では,福祉機器の選び方のポイント, 3Dプリンタを活用した福祉用具や科学的根拠に基づいたトイレの手すりについて,今後に役立つ情報を提供できればと考えております。
第21回 コロナ禍における情報リテラシー
第21回となる今回のテーマは、「コロナ禍における情報リテラシー」です。
テーマ設定の背景
新型コロナウイルスの影響が長期化する中、新型コロナウイルス感染症に関する様々な情報が溢れています。これらの情報の中には、科学的に不正確だったり、真実とは異なる情報や、誤解を招く情報が紛れ込んでいる場合も数多くあります。情報がたくさん溢れている世の中で、正確な情報を見抜くということは簡単なことではありません。
今回は、「コロナ禍における情報リテラシー」ということで、科学的な根拠が示されている情報や、行政機関や学会といった公的機関による発信などをお示しし、信頼できる情報源を選んで参照していくことについて、考えていく機会になればと思っております。
第20回 継続するコロナ禍で変化する私たちの生活
第20回となる今回のテーマは、「継続するコロナ禍で変化する私たちの生活」です。
テーマ設定の背景
新型コロナウイルスの感染防止対策は既に1年を越えて継続しています。毎日の生活や行動、仕事や働き方、社会生活の面で、私たちはこれまでと異なる対応を強いられてきています。こうした対応と変化が長期化することで、私たちの生活はすでに大きく変わりつつあるといっても過言ではありません。
今回は、コロナ禍での私たちの生活が、身近な高齢者や子どもの生活の面で、大学生の生活の面で、日々の社会での働き方の面でどのような変化となって現れているのか、その実態と対応を専門の先生方から紹介いたします。それぞれにこれまでにない変化と対応の状況が示されています。これらを通して、コロナ後の今後の生活の仕方や望ましい取り組みを、皆さんとご一緒に考える機会としたいと存じます。
第19回 私たちができるSDGsへの取組み
第19回となる今回のテーマは、「私たちができるSDGsへの取組み」です。
テーマ設定の背景
SDGsとは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発のための目標)」の略称で、「エス・ディー・ジーズ」と読みます。皆さんもカラフルなロゴマークを一度はご覧になったことがあるかと思います。
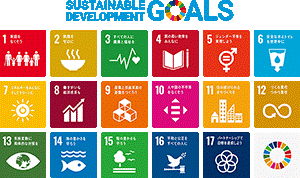
SDGs は、2015年9月に開かれた国連サミットで、2030年を年限とした国際社会が取組む目標指針として採択されました。基本理念を「No one will be left behind(誰一人取り残さない)」と掲げ、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のために、17のゴール(目標)と、169のターゲット(成果)を定めました。SDGsは開発途上国だけではなく、日本を含む先進国もその達成が求められている、普遍的な目標です。自然と調和しつつ、健康で自分らしく生きる社会をつくるために各国政府やNGO/NPO、企業や市民団体などが活動しています。
COVID-19の流行により、多くの人が健康を害し、経済の影響を受けました。今こそ、よりよい社会のあり方を考え、私たちができることを考える時です。しかしながら、自分の生活とSDGsがどのような関係にあるのか、実感がない方も多いかと思います。そこで、第19回のWEB講座では、SDGsの保健医療福祉や環境に関する目標について、市民レベルでできる取組みについてお伝えします。